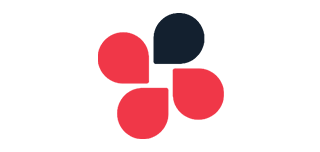執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
 前回の評価制度のご相談があった事例の続きになります。
前回の評価制度のご相談があった事例の続きになります。
理念等をベースとした評価制度に変更を進めていましたが、理念等の浸透を図ることを目的として、各理念等に対する目標設定を期初に従業員に立ててもらう行う方向で検討をされておりました。
評価制度の変更の目的としては、企業のフェーズとしてやや複雑な制度設計になっていたものをシンプルでわかりやすい制度にしたいという意向もありましたが、目標設定の検討の段階では、等級によっても理念に対する行動が異なることから、目標設定の難易度や等級毎の行動の定義を変更したり、完成された制度はシンプルな制度ではなくなっていました。結局のところ、細かく定義や設定をしないと評価者から「評価ができない」「評価が公平ではない」などの不満が挙がっているとのことで、経営層の意向により、あまりシンプルではない制度に変更になったようでした。
評価者が日頃か被評価者を観察していたり、評価者会議などによって公平に評価できる仕組みが整っているのであれば、シンプルな評価制度でも公平公正な人事評価制度の運用に近づけることは可能です。
人事制度の見直しのご相談があった際に、各制度の連動がバラバラになっているなどの場合は制度を作り直した方がいいと提案するケースもありますが、せっかく運用している人事制度ですので、一部の修正や運用方法を改善するだけでも機能するになるケースも多いように見受けられます。